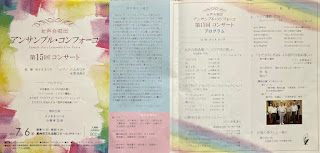7月12日(土)の午前中(9:30-12:00),奥州市の水沢教会で48回目となる合唱音楽研究会奥州の活動を行いました。土曜日の午前中のせいか,アンサンブル・コンフオーコの演奏会後一息ついているのか,参加者は少なめの20名ほどでしたが,4パートが揃って歌うことができました。
久しぶりに集まった感じがなぜかしたので,発声法についても基本的なこと,たとえば胸郭&横隔膜の動きや自然な吸気の作用など時間をかけて確かめました(アクシデントもありましたが皆様のお働きによって事なきを得ました。感謝いたします m(._.)m)。
その後,持参した《MIssa brevis》の音源を聴きながら《Gloria》を歌ってみました。音下がりへの対策です。演奏中に音が下がらない演奏をたくさん聞いて慣らすことで調を保つ感覚,あるいは調がずれる感覚を身につけられるのではないかという考えです。良い物にたくさん触れればそれが「普通」になります。つまり「「普通」のレベル」が上がります。同様に良い音楽を聴き慣れれば音楽における「普通のレベル」が上がると思ったのです。
実際にやってみると,音源を聞いた直後や音源に合わせて歌った直後は,音源がなくてもほとんど音下がり現象は起きません。でもしばらく自分達だけで歌っていると,音の取り方がルーズになって下がり始めます。ですから現時点での結論としては,月2回だけ頑張るだけでは身につかないので普段から何度も聞いて自分の耳を育てましょう,ということになりました。歌う(発声する)ということは筋肉運動ですから!
次回は"Credo"に挑戦です。音だけでなく歌詞も身についていないので,普段から何度も取り組んで「普通」のことにしていきましょう。
終わりに,7月6日(日)のアンサンブル・コンフオーコの演奏会をテーマに感想を交流しました。聴いた人,歌った人,双方の感想を聞くことができました。また7月2日の県高校合唱祭を聴いてくださった方もありましたので,感想をお聞きしました。こういうことも音楽や演奏への理解を深めることにつながると思っています。
【お詫び】次回の活動日を7月27日(日)とお知らせしていたのですが,1日早めて7月26日(土)に変更いたします。場所は水沢南地区センター,時間は(変則的ですが)13:20〜16:20とします。急な変更で申し訳ございません。たくさん練習し成果をもって集まれるといいですね。よろしくお願いします。